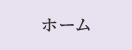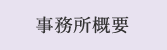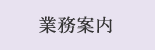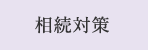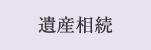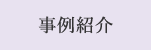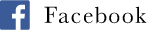不動産2025.04.14.検索用情報の申出とは?

はじめに
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。この義務の負担軽減のため、所有者が申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し職務上の権限(以下「職権」)で登記を行う仕組みが開始します。
この仕組みの開始に先立ち、令和7年4月21日以降に所有権の保存・移転等をする際には、所有者の検索用情報を併せて申し出ることが必要になります(義務)。
必要事項
検索用情報の申出を済ませておけば、住所等変更義務化後も、義務違反に問われることがなくなります。申出をすることで、自ら申請して費用がかかることもなくなります。では、検索用情報とはどのような内容なのでしょうか。具体的には、つぎの5点です。
⑴氏名
⑵氏名の振り仮名
⑶住所
⑷生年月日
⑸メールアドレス
⑴~⑷は、登記官が住基ネットで、住所変更の事実をシステム上で検索するためのものです。一方で⑸のメールアドレスがなぜ必要か疑問に思われるのではないでしょうか。これは、主に登記官が職権で名義変更をしていいかを確認するためのものです。新しい住所が公示(登記簿に新住所が記載される)されることに支障ある方に、了解を得た上で変更登記をするシステムになっています。ただし、メールアドレスは、「メールアドレスなし」というように登録しないこともできます。この場合は、職権登記の前提として、メールの代わりに書面を送付することが想定されています。
メリットデメリット
この検索用情報の申出の仕組みは、法務省自身が便利な制度と言っているように、メリットを感じる人は多いのではないでしょうか。しかしながら、メールアドレスの登録を前提としている点ついては、様々な意見があったようです。例えば、東京司法書士会のパブリックコメントでは、メールではなく、郵送で行うべきであるという意見がありました。大きく3つの理由があり、1つめは、メールアドレスの登録が必須なのであれば、その提供が新たな申請要件になることです。2つめは、登記名義人の電子メールの提供方法が他のネット上のサービような各種対策がされていないこと、フィッシングやなりすまし詐欺メールの防止策が言及されていないことです。3つめに、スマホアプリやSNSサービスへと変化している国民のIT利用状況を考慮すると、将来的にメールの利用が減少する可能性があることが挙げられていました。
私見
検索用情報の申出制度について、いち司法書士としては反対の立場です。理由は以下の通りです。
- 単純に業務量が増えるため
- メールアドレスへの連絡という手段が中途半端なため
- 住所の変更がいつ行られるか分からず、売買の登記手続き等の際にリスクがあるため
以下順番にご説明します。
単純に業務量が増えるため
これまでの登記申請では⑴氏名と⑶住所のみで登記申請していたところ、⑵氏名の振り仮名、⑷生年月日、⑸メールアドレスを確認し、登記申請書に記載しないといけません。実務的には⑵と⑷は面談時に確認するので情報をもらう労力はありませんが、⑸は完全に新しい項目のため手間が増えます。
メールアドレスへの連絡という手段が中途半端なため
まず、高齢の方であればメールアドレスが無い、又はほぼ見ないという方はかなりの割合でいらっしゃいます。また、メールを返さないと、住所変更を了解したことにならないので、住所変更をしないということになってしまいます。折角マイナンバーという制度を導入したのであれば、マイナンバーに関連したサービスでの連絡や携帯番号などの手段も併用してもいいのではないでしょうか。
住所の変更がいつ行られるか分からず、売買の登記手続き等の際にリスクがあるため
職権で住所変更がされる場合、いつ登記がされるのか分からず、例えば、売買の登記の当日などにされてしまった場合、登記が申請されないというリスクがあります。
後書き
反対とはいえもう決まってしまった制度ですので、対応しなければなりません。
弊所では以下の通りの運用予定です。
相続登記等相続関連での登記申請の場合、事前に書面で制度のご案内をし、メールアドレスの登録の有無をご選択いただきます。
売買の登記は基本的には仲介業者様等を通じてのご依頼が多いため、決済での面談時に直接登録の有無を確認する予定です。
検索用情報の申出についてのご相談はお気軽にご連絡ください。
(文責:川内)
-----------------------------------------
司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士
神楽坂法務合同事務所
代表 庄田 和樹
東京都新宿区神楽坂4丁目1番1号 オザワビル6階
TEL03-5946-8698 FAX03-5946-8699