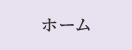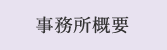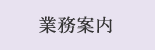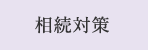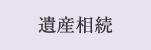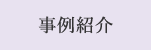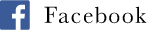不動産2025.03.24.長年放置していた相続登記をするにあたって
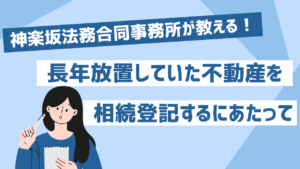
はじめに
2024年4月に相続登記が義務化されたことで、今まで放置していた不動産の名義変更に手を付け始めようと思うといった内容のお問い合わせをいただくことが増えました。ご相談をいただく時点で最終的にどなたの名義にしたいのか相続人間で話がまとまっている場合、簡単に名義変更ができるイメージをお持ちの方が多いですが、長年登記をしていなかった不動産はとくに複雑な手続きが必要になる場合が多いです。といいますのも、名義変更をするための登記手続きは、そのルールが細かく決まられており、おそらくみなさまが想像するよりも多くの書類が必要になるからです。とくにご相談が多くよせられる下記のケースは要注意です。
①登記簿上の名義人が何代も前のご親族である場合
まず現在の相続人を確定するために、大量の戸籍謄本が必要になります。名義人である被相続人や既に亡くなった相続人の方の出生から死亡までの戸籍一式が必要になることが多く、兄弟姉妹がたくさんいらっしゃったり、転籍をされている方が多いと、必要な戸籍をそろえるだけでも数か月単位で時間を要することになりますし、集まった戸籍の束はとんでもない厚みになり、読み解くのは至難の業です。
そして、どなたかに名義を寄せる場合は、集めた戸籍から特定した相続人全員の実印を押した遺産分割協議書と印鑑証明書もそろえる必要があります。普段連絡をあまり取らない遠い親戚に書類を送って事情を説明し、印鑑証明書を預けてもらうことはとてもハードルが高いのではないでしょうか。また、相続人の把握が漏れているなんてこともあり得ます。
②所有権保存の登記がされていない場合(表題登記しかされていない場合)
①の場合に加えて、最近ご相談が増えてきたのがこちらです。本来、登記簿は表題部と権利部からなりますが、たまに何らかの理由で表題部の登記しかされていない状態で今日まで至っているものもあります。とくにやっかいなのが、表題部の所有者欄に住所の記載がない場合です。
相続登記を申請するには、被相続人と登記簿上の名義人が同一人物であることを示す必要がありますが、そもそも登記簿上に住所の記載がなければその証明は不可能です。よって他の書類によって補うことになりますが、具体的にどういった書類が必要になるかは具体的事情によって異なりますので、場合によっては法務局に事前に確認する必要もあり、通常より多くの手間を要します。
上記のような複雑なケースは、ご自身で解決しようとすると話がこじれてしまい上手くいかないことも多々ありますので、ぜひ早い段階で私ども司法書士にご相談ください。
(文責:坂田)
-----------------------------------------
司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士
神楽坂法務合同事務所
代表 庄田 和樹
東京都新宿区神楽坂4丁目1番1号 オザワビル6階
TEL03-5946-8698 FAX03-5946-8699