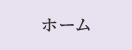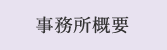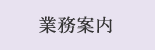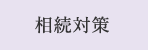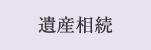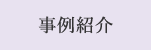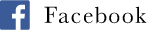事例紹介2025.04.21.相続土地国庫帰属制度 ~申請から承認までの実例~
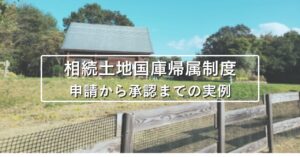
はじめに
令和5年4月27日の相続土地国庫帰属制度開始後ご相談を承ることが多いなかで、当所で実際に行った、申請から承認までの実例をご紹介します。
まずは、相続土地の国庫帰属の申請先と申請手続きの概要を紹介します。
相続土地の国庫帰属の申請先
相続土地の国庫帰属の申請先は、土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局です。ただし、土地の所在地を管轄する法務局が遠方の場合は、近くの法務局から申請する事ができます。
申請手続きの流れ
申請手続きは、以下の流れで進行します。
①承認申請
承認申請書などの必要書類を提出し、さらに所定の審査手数料を納付して承認申請を行います。
主な必要書類は以下のとおりです。
・承認申請書
・承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
・承認申請に係る土地及び当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
・承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
・申請者の印鑑証明書
・固定資産税評価額証明書(任意)
・申請土地に辿り着くことが難しい場合は現地案内図(任意)
・承認申請土地の境界等に関する資料(あれば)
②書面審査・実地調査
法務局担当官が申請書類を審査し、対象土地の実地調査が行われます。却下事由に該当する場合は申請が却下され、不承認事由に該当する場合は申請が不承認となります。
③承認
却下事由も不承認事由もない場合は申請が承認され、承認された場合は負担金額が申請者へ通知されます。
④負担金の納付
申請者は、負担金額の通知を受けた日から30日以内に所定の負担金を納付しなければなりません。納付を怠った場合、承認決定が失効します。
⑤国庫帰属
負担金の納付時をもって、対象土地の所有権が国庫に帰属します。
実例
ご依頼内容は、帰属したい土地は山林4筆。隣接しあったA番1とA番2、隣接しあったB番1とB番2という内容です。
・現地の写真撮影と必要書類の作成
ご依頼者様も現地には行ったことがなく、現地の状態が地図上でしか分からない状況で、対象地がかなり遠方だったため、地元の業者に協力してもらい、申請書類に必要な現地の写真関係を撮っていてもらいました。
撮った写真をもとに書面を作成し、承認申請書も自身で作成する必要があります。
・近くの法務局へ無料相談
準備した申請書類等を持参して近くの法務局へ無料相談へ出向きました。ここで申請書の細かい部分を指摘してもらい、土地の所在地を管轄する法務局に資料を事前に共有してもらいました。
A番1とA番2には笹が生えており、却下要件の『除去しなければ土地の通常の管理・処分をすることができない有体物が地下に存する土地』に該当してしまうため、伐根伐採し更地にしたうえで申請を進めました。
さらにB番1とB番2は登記上「山林」でしたが課税上「公衆道」となっていました。法務局へ事前相談しましたが「申請してみないと分からない。」とのことだったので、ご依頼者様と相談のうえ却下前提で申請を行いましたが、やはり結果は却下となりました。
申請してから最終結果に至るまでは1年以上かかり、かなりの時間を要しました。
実際にかかった負担金について次回のコラムにてご紹介しますので、そちらもご一読ください。
このように、書類の準備だけでなく、要件を満たしているかの確認、承認後は負担金が発生する等、かなりの手間と時間とお金がかかります。自身で対応するのは、一般の方では労力がかかりますので、私共のような専門家にご相談ください。
(文責:川添)
-----------------------------------------
司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士
神楽坂法務合同事務所
代表 庄田 和樹
東京都新宿区神楽坂4丁目1番1号 オザワビル6階
TEL03-5946-8698 FAX03-5946-8699