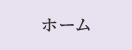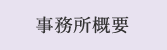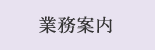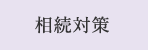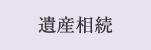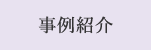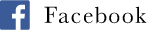事例紹介2025.04.21.相続土地国庫帰属制度とは

はじめに
土地を相続したものの「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りに迷惑がかからないようにきちんと管理するのは経済的な負担が大きい」。そのような理由で相続した土地を手放したいとき、その土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」という制度があります。この制度は令和5年4月27日から開始されました。
1. 相続土地の国庫帰属を申請できる人
相続土地の国庫帰属を申請するには、一定の申請要件を満たさなければなりません。申請できるのは、原則として、以下の要件をいずれも満たす人です。
・相続人であること
・相続または遺贈(遺言による贈与)により、土地または土地の共有持分を取得したこと
従って、土地または土地の共有持分の遺贈を受けた人でも、相続人でなければ相続土地の国庫帰属は申請できません。ただし例外的に、相続人が相続または遺贈により土地の共有持分を取得した場合、その相続人と共同であれば、ほかの共有者も土地の国庫帰属を申請できます。
ただし、生前贈与で土地を受けた相続人は、相続や遺贈で土地を取得したわけではないため、国庫帰属の申請はできませんし、法人が所有している土地の場合も対象外となります。
2. 国庫帰属が認められる相続土地の要件
帰属が認められる土地は、法令で定める却下事由と不承認事由のいずれにも当てはまらないものに限られます。
却下事由と不承認事由について、詳しく説明します。
【申請の段階で却下される土地(却下事由)】
以下の土地は、国庫帰属の申請自体が認められません。
・建物が建っている土地
・担保権または使用・収益を目的とする権利が設定されている土地
・通路用地、墓地、境内地、水道用地、用悪水路、ため池が含まれる土地
・特定有害物質により汚染されている土地
・境界が明らかでない土地など、所有権の存否・帰属・範囲について争いがある土地
【申請しても承認されない土地(不承認事由)】
以下の土地は、国庫帰属の申請が不承認となります。
・勾配30度以上・高さ5メートル以上の崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用・労力を要するもの
・土地の通常の管理・処分を阻害する工作物・車両・樹木そのほかの有体物が地上に存する土地
・除去しなければ土地の通常の管理・処分をすることができない有体物が地下に存する土地
・以下の土地であって、現にほかの土地の通行が妨げられているもの
a.公道へ通じない土地
b.池沼・河川・水路・海を通らなければ公道に至ることができない土地
c.崖があって公道と著しい高低差がある土地
・所有権に基づく使用または収益が厳に妨害されている土地(その程度が軽微で、土地の通常の管理または処分を阻害しないと認められるものを除く)
・以下のいずれかに該当する土地
a.土砂崩れなど土地の状況に起因する災害が発生し、その災害により生命・身体・財産への被害が生じるおそれがあり、その被害の拡大・発生を防止するために、土地の現状に変更を加える措置(軽微なものを除く)が必要なもの
b.動物が生息する土地であって、その動物により人の生命・身体や農作物・樹木に被害が生じるおそれがあるもの(その程度が軽微で、土地の通常の管理・処分を阻害しないと認められるものを除く)
c.主に森林として利用されている土地のうち、市町村森林整備計画に適合していないことにより、追加的に造林・間伐・保育を実施する必要があると認められるもの
d.国庫帰属後の法令に基づく処分により、国が通常の管理に要するもの以外の費用に係る金銭債務を負担することが確実な土地
e.法令に基づく処分により、承認申請者が所有者として金銭債務を負担する土地であって、国庫帰属後に国が法令に基づきその金銭債務を承継するもの
反対に、却下事由と不承認事由のいずれにも該当しなければ、相続土地の国庫帰属が承認されます。
取得した土地を自分で活用することができず、売却もできない土地を所有している人が検討するのが、相続土地国庫帰属制度です。上記のように要件が細かく定められているため、まずは帰属対象の土地なのかを把握する必要があります。
次回は、実際に当所で相続土地国庫帰属制度の書類作成代理人として承った事例を紹介します。
(文責:川添)
-----------------------------------------
司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士
神楽坂法務合同事務所
代表 庄田 和樹
東京都新宿区神楽坂4丁目1番1号 オザワビル6階
TEL03-5946-8698 FAX03-5946-8699